ハンバートハンバートの歌を聴いていると、「なぜこんなに胸に刺さるんだろう?」と不思議に思うこと、ありませんか?!
優しい声で穏やかに歌われているのに、歌詞をよく耳にすると吃音や発達障害、生きづらさといった、普段は語られにくいテーマが描かれていることがあります。
代表曲「ぼくのお日さま」や「がんばれ兄ちゃん」は、ただの応援歌や癒しの歌ではなく、弱さや孤独を抱える人の姿をまっすぐに映し出した名曲!
だからこそ、「どうしてそんなテーマを歌うの?」「もしかしてメンバー自身が病気なの?」と気になる人も少なくありません。
こちらでは、そんな疑問を解き明かしつつ、歌詞に隠された本当の意味を深掘りしていきます。
読んだ後には、きっと彼らの音楽が違って聴こえるはず!
ハンバートハンバートが障害の曲を歌ってるのはなぜ?


ハンバートハンバートの歌を聴いて「障害」や「鬱」という言葉を連想する人は少なくないようです。
でも、ここで最初に強調しておきたいのは、メンバー本人(佐野遊穂さん、佐藤良成さん)に障害や病気の事実は一切ないということ。
お二人はとても健康で、家族や日常を大切にしながら音楽活動を続けています。
それではなぜ「障害」というイメージが結びついてしまうのでしょうか?
その理由は、ハンバートハンバートの楽曲テーマや作品提供の背景にありました!
「障害」と検索される理由
実際に「ハンバートハンバート 障害」と検索されることが多いのは、次のような背景があるからです。
- 『ぼくのお日さま』の歌詞
この曲は、吃音(言葉が詰まる障害)を抱えた少年が主人公。
その気持ちに寄り添う形で書かれた楽曲が、障害や生きづらさと強く結びついています。 - 歌詞のテーマに「言葉が出ない苦しみ」「自己肯定感の低さ」が描かれている
代表曲「ひかり」や「ぼくのお日さま」では、社会の中でうまく馴染めない人の気持ちや、弱さを抱えながらも前に進もうとする姿が歌われています。 - 「鬱」「死」なども検索されている
これはメンバー本人の状態ではなく、楽曲に描かれる「絶望」「喪失」「再生」といったテーマが影響しているためです。
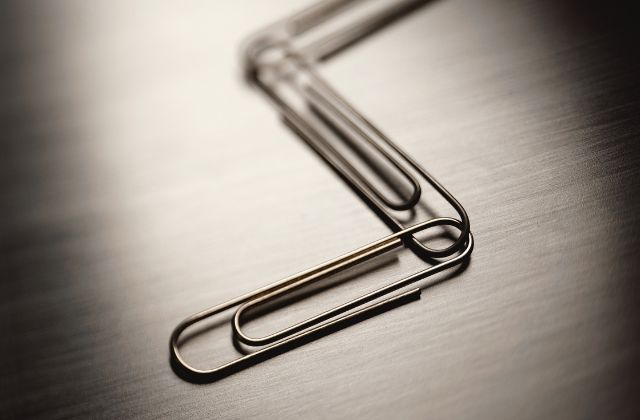
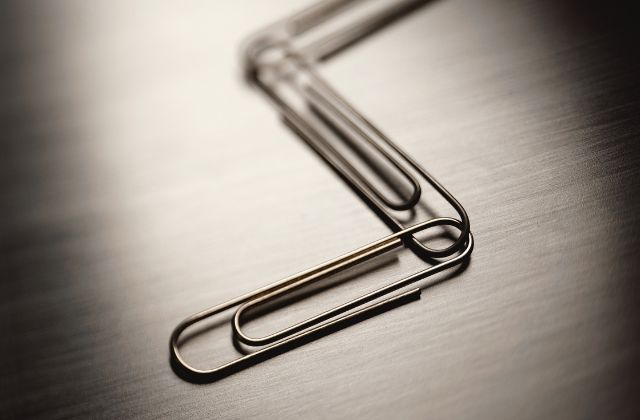
実際の彼らの姿
メンバー自身は障害や病気を公表したことはなく、現在も健康的に活動しています。
また、「死」と検索されることがあるのは、かつてマネージャーを務めた山口周さんが亡くなったニュースが影響しているためのようです。
つまり、これはメンバー自身の体調や病気とは関係ありません。
なぜ障害の曲を歌うのか?
ハンバートハンバートがこうしたテーマを歌う理由は、社会の中で声に出しにくい気持ちに光を当てるためと考えられます。
ハンバートハンバートの歌は決して説教臭いものではなく、あくまで「隣でそっと寄り添ってくれる」ような存在。
だからこそ、障害や病気を抱える人たちが「自分の気持ちを代弁してくれている」と感じやすいのではないでしょうか。
ハンバートハンバートのメンバーが吃音や発達障害を持ってるの?
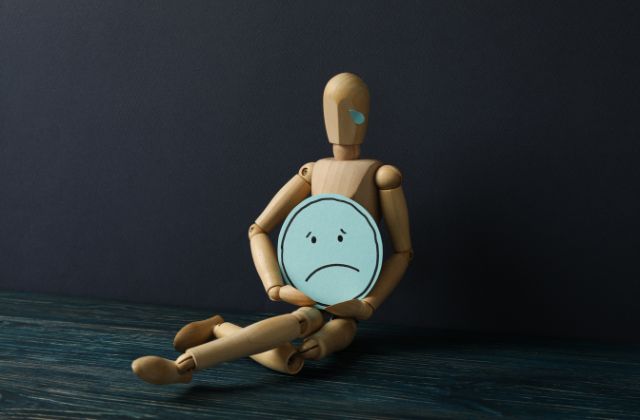
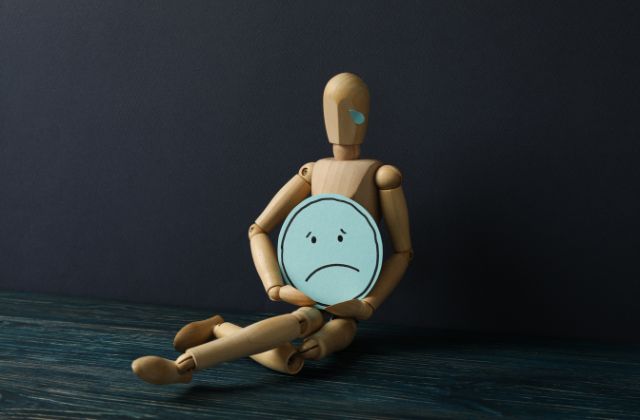
メンバーの病気
ハンバートハンバートの楽曲というと、「吃音」や「発達障害」の曲が自然に頭に浮かぶ人もいるかと思います。
でも、すでにお伝えした通り、メンバー本人(佐野遊穂さん、佐藤良成さん)が発達障害や吃音を公表している事実は一切ないということ!
二人は健康で、夫婦として日常や家族を大切にしながら音楽活動を続けています。
障害をテーマにした曲がある
- 「がんばれ兄ちゃん」
発達障害(広汎性発達障害、ADHD、知的障害など)の兄を主人公に、妹や家族の視点で応援する歌です。
普通とは違うことで生きづらさを抱えながらも懸命に生きる兄の姿、家族の優しさ、社会の冷たさまで繊細に描かれています。 - 「ぼくのおひさま」
吃音に悩む少年の苦しさやもどかしさ、自分らしさを受け入れる希望を優しく表現した曲です。
障害者や生きづらさを感じる人々から強く支持されています。
「ぼくのおひさま」は2014年のアルバム『むかしぼくはみじめだった』に収録されており、このアルバムのタイトルも「もしかしてメンバーが吃音だったの?」という誤解につながっているのかも。
メッセージ性
ハンバートハンバートの音楽は、発達障害の当事者や家族だけでなく、あらゆる生きにくさを抱える人に向けた応援歌でもあります。
- 弱さや孤独に寄り添う
- ありのままの自分を肯定する
- 日常の中の小さな希望を見つける手助けをする
歌詞の中で、誰にでもある心の弱さや孤独に深く向き合う曲が多くあります。
ハンバートハンバートは、穏やかな歌声と優しいハーモニーの中に、誰もが抱える心の葛藤や困難に寄り添うメッセージを込めることで、多くのリスナーの心を支えている夫婦デュオ!
ハンバートハンバートの吃音や発達障害の曲の歌詞の意味を探る!


ハンバートハンバートの楽曲には、吃音や発達障害など「生きづらさ」に寄り添ったテーマが多く見られます。
その中でも特に代表的な曲が「ぼくのお日さま」と「がんばれ兄ちゃん」です。
どちらも障害を持つ人々やその家族の視点を丁寧に描き、聴く人に共感と勇気を届ける作品となっています。
「ぼくのお日さま」の歌詞の意味
- 吃音の少年の心情をリアルに描く
歌いだしから「ぼくはことばがうまく言えない」「はじめの音でつっかえてしまう」「ことばがのどにつまる」と、吃音によるもどかしさや孤独がそのまま表現されています。
重要なことを伝えたいのに言葉が出てこない胸の痛みや切実な感情が、聴き手にも伝わるようになっています。 - 希望と救いの表現
歌の中では、歌うことや「お日さま」が象徴的に登場し、言葉で伝えられない気持ちを受け止め、自由に表現できる場として描かれています。
つまり、苦しみの中にも光や希望があることを示しており、聴く人に安心感や励ましを与えています。 - 作品背景との連動
この曲は2014年のアルバム『むかしぼくはみじめだった』に収録されています。
吃音の少年の成長や心の葛藤、希望が丁寧に描かれています。


「がんばれ兄ちゃん」の歌詞の意味
- 発達障害の兄と家族の視点
発達障害を持つ兄を主人公に、妹や家族が彼を応援する視点から歌われています。
普通とは少し違うことで生きづらさを抱える兄が、懸命に生きる姿が描かれ、家族の優しさや支えも同時に表現されています。 - 生きづらさへの共感と励まし
弱さや困難を抱える兄の姿を通して、聴き手自身も自分の生きづらさに寄り添い、希望や勇気を得ることができる内容です。
家族愛や応援のメッセージが強く、感動的な歌詞となっています。
共通するテーマ
- 生きづらさに寄り添う
- 困難に立ち向かう姿を描く
- 希望や救いを歌う
ハンバートハンバートのこれらの曲は、障害や吃音の苦しみだけを描くだけでなく、その中にある小さな希望や家族の温かさ、自由に表現できる喜びを丁寧に描き出しています。
歌詞の中に込められた思いは、障害の有無にかかわらず、たくさんの人の心に寄り添い、勇気や感動を与えてくれています!
まとめ
ハンバートハンバートが吃音や発達障害をテーマに歌う理由は、決してメンバー本人に病気や障害があるからではありません。
佐野遊穂さんと佐藤良成さんは健康で、日常や家族を大切にしながら音楽活動を続けています。
それでも、彼らの楽曲には生きづらさや障害に寄り添う温かい視点が反映されており、多くのリスナーに共感と勇気を届けています。
例えば、「ぼくのおひさま」では、吃音に悩む少年の気持ちを丁寧に描き、言葉にできないもどかしさや孤独を歌いながらも、歌の中で自由に表現できる希望を感じさせます。
一方、「がんばれ兄ちゃん」では、発達障害の兄を家族が応援する視点から描かれ、弱さを抱えながらも懸命に生きる姿や家族の愛情が心に響きます。
これらの曲に共通するのは、単に障害や困難を描くだけでなく、希望や支え、勇気を与えるメッセージを含んでいる点です。
歌詞の中では、誰もが抱える弱さや孤独、社会の壁と向き合う姿を丁寧に描写しており、障害や生きづらさに限らず、多くの人の心に寄り添います。


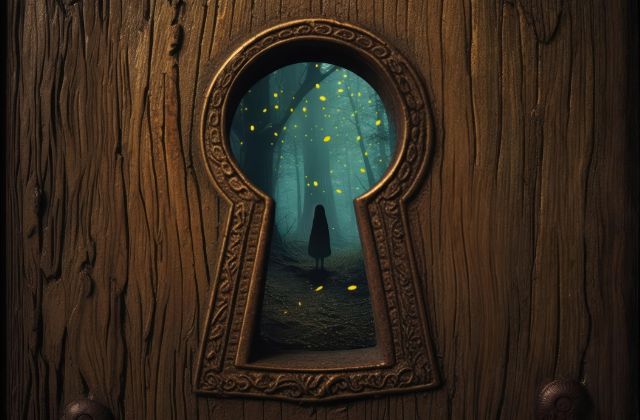






コメント